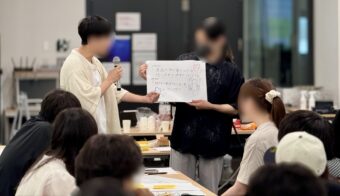プロフィール
「その学び、次につながっていますか?」
私は、問いから始まる学びを “その場限り” で終わらせないデザインをしています。問いが行動になり、行動が社会に届く。そんな “循環型の学び” をデザインするワークショップデザイナーです。
正解がない時代、違和感やモヤモヤの中にこそヒントがある。だからこそ「問い」を立て、言葉にならない声に耳をすませます。
これまで、企業ではDX人材育成や新規事業開発、大学や学会では異分野連携や人間中心設計(HCD)教育、地方では市民と行政の共創による未来づくりの対話の場を、また、分野を問わず、生成AI活用やAIとの付き合い方などをデザインしてきました。
参加者、依頼者、社会、そして自分自身。関わる全員にとって「やってよかった」と思える “意味ある場” をつくる。
それが、私が目指す「四方良し」のワークショップです。
(ワークショップデザイナーユニット「グリサン」主宰)
認定WSD資格 取得年度
2024
主な活動地域
全国。首都圏を活動拠点としていますが、全国どこでも伺います。
私のワークショップを語る3つのキーワード
※ワークショップにおける自分自身の「特質」を踏まえたキーワード3つを説明しているものです。
「問い」からはじまる
「腹落ち感」が生み出す
「四方良し」を目指す
1. 「問い」からはじまる
“モヤモヤ”に意味がある時代。問いから始める変化のデザイン
本質的な課題発見 正解のない時代に求められるのは、答えを出す力以上に「本質的な問いを立てる力」です。ワークショップでは、参加者の漠然とした課題意識や違和感を、対話を通じて「問い」へと昇華させます。目の前の事象(具体)と本質(抽象)を往復する思考プロセスを通じて、AI時代に不可欠な「自ら考え、課題を見抜く力」、すなわち組織の思考体力を鍛えます。
2. 「腹落ち感」が生み出す
「それ、終わったら忘れられる学びになってない?」学びを循環させる仕組みを考える
持続的な行動変容 研修で知識を得るだけでは、現場の行動はなかなか変わりません。だからこそ、私は参加者の「腹落ち感(深い納得感)」を何よりも大切にしています。知識のインプットだけでなく、あえて非効率に見えるアナログな対話や共創を通じて、参加者は心から納得し、課題を「自分事」として捉えます。この強い当事者意識が「やらされ感」のない自発的なアクションを生み、現場での持続的な行動変容を促します。
3. 「四方良し」を目指す
「誰か一人の満足でいいの?」ワークショップを四方良しで設計する視点
未来を共創するデザイン ワークショップは、関わるすべての人にとって価値ある体験であるべきだと考えます。「参加者の満足」「依頼者の課題解決」「社会への貢献」、そして「提供者自身の成長」。この「四方良し」の実現をデザインの核に据えています。目先の成果だけを追うのではなく、多様な視点が交差することで生まれる創造性を大切にし、関わるすべての人が未来に希望を持てるような、持続可能な価値を共創します。
ワークショップ実績
https://note.com/gurisan_ws/n/n64134bc300ba
2025年7月:「【新価値創出】コア技術を異分野へ! 〜既存技術から新たな価値を生み出す〜」日本画像学会 Imaging NEXT
2025年7月:「人間中心設計入門」東京工芸大学 特別講義
2025年6月:「AI ツールの連携活用ハンズオン体験~試行と共有を通して “応用レシピ” を描き出す〜」日本画像学会年次大会ワークショップ
2025年 3月:「HCD基礎検定ミニワークショップ-体験と共感で、あなたの未来を切り拓く」人間中心社会共創機構
2025年 3月:「不確実な変化に対応するITサービスを生み出す-シナリオプランニング起点のワークショップ」大手SIer DX人財育成
2025年 2月:「HDC実践者向け ワークショップで学ぶワークショップデザイン」セミナー 人間中心設計推進機構
2024年12月:「究極 vs 最悪!? パソコン教室の未来を創ろう!」ハロー!パソコン教室 スタッフ向け
2024年12月:「ラベルを剥がして未来を創る:アンラーニングで拡がる新しい世界」日本画像学会シンポジウムワークショップ
2024年11月:「生成AIを仲間にして未来を描こう!(あなたとおおさき未来デザイン会議 DAY1)」鹿児島県大崎町住民参加
2024年10月:「Culturing ensemble workshop 」未習得の楽器演奏を前提とした即興合奏 日本音楽教育学会
2024年10月〜11月:「人間中心デザイン特論」授業(全15回) 非常勤講師 東京都立産業技術大学院大学
2024年 8月:「学部の壁を越える!異分野コラボレーションワークショップ」玉川大学 学生向け
2024年 6月:「イメージングカフェワークショップ 今後の学会イベントアイデアを創出」 日本画像学会年次大会ワークショップ
2024年 2月:「ゴミ分別リサイクルあるある みんなのアイデア交換ワークショップ」鹿児島県大崎町住民参加